もののつくりかたを見なおす
デザイナーによるセルフプロダクションから見えること
いつも、あるべきものを考えていた
吉田氏は、日本の工業デザインの礎を築いた柳宗理氏の下で、そのキャリアをスタートさせた。そこではクライアントのある仕事とは別に、自らが企画したものを企業に製品化しないかと提案する習慣があったという。企業が売りたいものと、自分たちが考えるあるべきものが必ずしも一致しないからだ。

異なるサイズでも積み重ねられるナラ材のトレイ

子供でも片手で持ち上げられる形状の茶碗
流通させて分かること
2011年に独立した後も、その考えをもとにセルフプロダクションを行っている。新潟の金属加工工場ではステンレスのキッチンウェアを、九谷焼の製陶所では子供のための器などをつくってもらい、販売している。いずれも手に馴染みがよく端整な造形、そして何より、つくり手のものへの愛情を感じさせる道
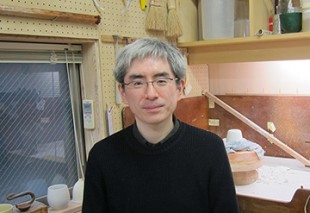
ヨシタ手工業デザイン室の吉田守孝氏
具たちだ。 「規模が小さくとも製品を流通させることが重要」と、吉田氏は言う。生産や販売といったデザイン以外の部分を知ることができるし、何よりも、自分が欲しいと思うものを欲しい人がいるという確認ができるからだ。 最近では、それらの作品を見て彼の考えに共鳴する企業から、製品のデザインを依頼されるという好循環が生まれている。
あるべきものとは何か。吉田氏と話していて、それはきっと人々の生活の豊かさに寄与するものだろうと思った。ややもすると目新しさを追求したり、コストを抑えることばかりに気をとられがちなものづくりの現場で、忘れてはいけない視点に気付かされた。


